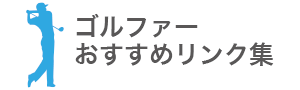平成生まれ作家のサバイバル術~朝井リョウ~
アイドルやスポーツといった若さが必要条件となる世界を除いて、若くして世に出るということは、紛れもなく偉業である。裾野が広く、実力者が軒を連ねるエンタメ系小説の世界でのそれは、奇跡にも似た「事件」である。
史上最年少、23歳で直木賞を受賞した作家、朝井リョウの登場。それは、文芸界の重大ニュースである。
直木賞受賞作となった『何者』(新潮社)は、ツイッターを始めとしたSNSや就職活動を物語に落とし込んだ作品。この作品は、一方では、若者の「こころの有り様」を代弁し、他方では、もうすでに「若くなくなった」人々へ若者の「今」を解説してみせている。
読み手のバックグラウンドに制約されないがゆえに物語の生息領域は広く、直木賞受賞作というアナウンス効果がその範囲を押し広げている。今回は、この文芸界の若きプリンスについて考えたい。
◇平成生まれ作家のサバイバル術◇
このコラムを書くにあたり、周囲に「朝井リョウくんって知ってる?」と聞いて回った。予想に反し、その答えの多くは「知らない」だった。
しかし、彼のデビュー作『桐島、部活やめるってよ』(集英社)は、ほぼすべての人が知っていた。
昨年この小説を原作とした映画が公開されたという事情もあるが、世間のこの作品の認知度は高い。その理由は、印象的なタイトルにあると思う。村上龍のデビュー作『限りなく透明に近いブルー』(講談社文庫)にも似た一度聞いたら忘れられないフレーズ。コアな文芸ファンならこのタイトルだけで買いだ。このような作品タイトルをつけられる作家の作品にハズレがないことを経験で知っているからだ。
この作家が生まれた1989年。それは、わずか数日の昭和64年を残し、元号が平成になった年だ。バブル経済が収束過程に入り、その後スタートする「失われた××年」の日本。かつて××には、10という数字が入ったが、今は20に修正されている。縮小再生産を余儀なくされる日本で過ごし、過ごしているというバックグラウンド。なんとなく、よくなるだろうという感覚で「若者である時間」を過ごしたそれ以前の世代とは異なり、漠然とした不安の中でその時間を過ごしている彼には、必然と備わったのかな思われる技術が作品に担保されている。
作家が生き残るための手段のひとつは、コアな読者を掴むことである。23歳の青年作家がターゲットとすべき対象は、だれだろうか?そんな思索があったのか、文体に小説好きの若い女性(文芸的感性が若いという意味も含む)読者への意識が伺える。
俺は、星と星をつないでいくように、スーパーの中を慌しく動く。俺が動いたところを線でつないでいけば「ひとり暮らし」という星座ができそうだ。(『何者』より)
こういう文章を散りばめ、破綻のない物語を書き、読者の期待を「大筋で裏切らない」ストーリー展開を担保できる作家は、強く、安定的な作家といえるだろう。この青年作家の作品は、そこがきちんと押さえられている。安定的とはもちろん、一定の部数を売ってくれるという意味である。
この作家が、すごいのはこの後に、次のように続けられるからだろう。
ついいつも、買ってしまう、牛乳の近くに置かれている乳製品のカップデザートを今日はふたつ。
読者女性の「そうそう、つい買うよね」「そういう気持ちわかる」というツッコミが聞こえてきそうである。「共感」は、現代の若い女性を動かすキーワードだ。主人公の青年の日常生活の描写に読者が共感できる部分をさりげなく挿入できるバランス感覚。
この記述がすごいのは、今の若者は、乳製品のデザートが牛乳の側に置かれている理由もわかっていることを前提に書かれているからだ。スーパーの商品陳列の戦略にハマっているのはわかっているけれど、それでも「ついいつも、買ってしまう」と書かれているから共感の密度が濃くなるのである。
新古書店の隆盛やネットによる中古本の販売網も確立している現代、新刊本はなかなか売れない時代になってしまった。そんな時代にデビューする若者は、当然にしたたかでなければならない。物語の鮮度が重要なだけでなく、このような細かいテクニカルな部分も担保されないと生き残れない。そう感じているのだろうと推定できる平成生まれの青年作家のサバイバル感覚は、既存の作家の傲慢さを射抜くほどの力があると思う。
「現代の若者はこういうもの」なんて簡単に理解できると思うなよ。
そんな声が作品から聞こえてきそうである。