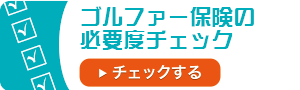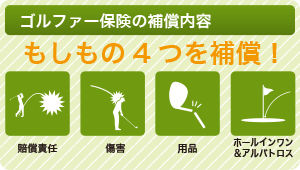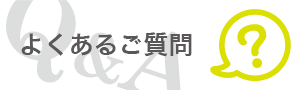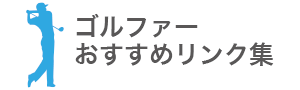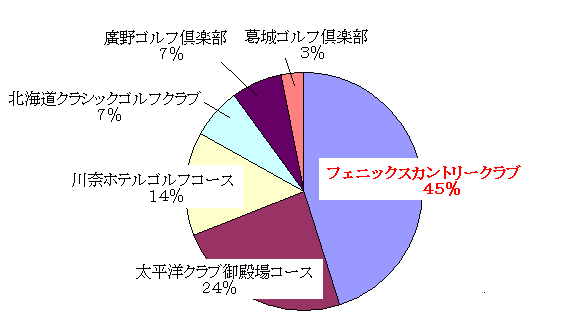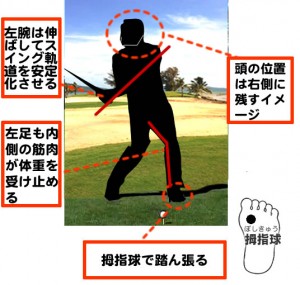イノベーションの萌芽~ゴルフのミライ~
オーストリアの経済学者、シュンペーターは言った、「イノベーションが経済を発展させる」と。もし、それがゴルフの発展にもあてはまるのだとするならば、ゴルフのイノベーションとは、何であろうか?技術革新であろうか、新しいサービスだろうか、全く新しいゴルフ理論であろうか。
イノベーションの萌芽~ゴルフのミライ~は、あらゆるゴルフの新しい胎動に着目。その未来を考察する。
今回は、帝人株式会社(大阪市)グループが開発した、新素材「ナノフロント(R)」に着目する。
nano(ナノ)。ミリが0.001(千分の一)を表すのに対して、ナノは、0.000 000 001(十億分の一)を示す。帝人が開発した、ナノフロントは、繊維1本あたり700ナノメートルの細さ。メーカー発表値で、髪の毛の約1/86、断面積換算では、約1/7500の細さしかない。この細い細い繊維がゴルフを変えようとしている。
アクシネットジャパン(東京都江東区)は、この細い繊維に着目。『ナノロック』の製品名で「フットジョイ」ブランドのグローブに採用した。細い繊維で何が変わったのか?それは、
・皮膚との接点が小さくなったため、高い密着感と適度なつけ心地を実現。密着感は、高いグリップ力を生む。
・細い繊維ゆえに、繊維間の隙間が広く通気性と撥水性が高くなった。不快な蒸れもなく、雨や汗に強い。
であるが、それ以上に革命的となったのは、その薄さだ。
細い繊維ゆえに実現した薄さは、従来のグローブの概念を覆した。天然皮革や人工皮革のグローブが主流であるゴルフグローブゆえに、その薄さは異端に感じるゴルファーもいるだろうが、その感覚は、これまで薄いグローブが存在しなかったゆえだと思われるのだ。そもそも、グローブに一定の厚さが必要だという理由はない。むしろ、素手に近い感覚はゴルファーの要望に近いはずだ。
この薄いグローブ誕生は、ゴルフグローブの大きな分岐点になるだろう。グローブに素手に近い感覚を求めるゴルファーは、このグローブを手放さないはずで、この市場の一定の支持層となると考えられる。このグローブが浸透するにつれて、決して少なくないゴルファーがこの薄いグローブへ乗り換える可能性は十分だ。
ナノロックの成功によりダンロップ、ブリヂストンもこの分野に参入。供給体制も整いつつある。
このナノフロントは、素材にポリエステルを使用している。ポリエステルは、被服に多く活用されており、大半のスーツの裏地はポリエステルである。また、ペットボトルの素材もこのポリエステルの仲間である。
筆者がナノフロントに着目するのは、帝人が取り組んでいる「繊維を細くする技術」へのアプローチの進展にある。ナノフロントは、比較的構造が単純なポリエステルが素材であるが、今後この技術が発展すれば、ポリエステル以外の素材で細い繊維がうまれてくるだろう。その都度、画期的なゴルフ用具がうまれる可能性が高い。さまざまなメーカーがゴルフ用具への応用を試みることが予想されるからだ。グローブはもちろん、グリップ、ウエア、キャップ(サンバイザー)に留まらない発展が期待される。
そう遠くない将来に、私たちは天然芝とほとんど変わらない風合いをもつ人工芝でパットの練習をしているかもしれないのだ。
たとえ、小さなテクノロジーの進化であっても、ゴルフへ影響を与える。ゴルフは技術と資本の親和性が高い分野だ。いろんな「今」着目し、ゴルフへの波及効果を考えることもゴルフの楽しみの一つであるといえる。